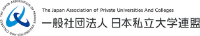MEMBER
A氏
日本私立大学連盟加盟大学職員
入職20年目

B氏
日本私立大学連盟加盟大学職員
入職8年目

C氏
日本私立大学連盟加盟大学職員
入職4年目

D氏
日本私立大学連盟加盟大学職員
入職13年目

司会音 好宏
上智大学文学部教授、
広報・情報委員会大学時報分科会分科会長

1-1大学業界への転職
教育に携わることができる魅力
音 現在、社会全体で労働流動性が高まっており、前職で培ったスキルを新たな職場で生かすという流れも当たり前になっています。そのような中、私立大学においてもさまざまなスキルを持った人材に対するニーズが高まっており、職員の中途採用も増加しています。その一方で、大学の主たる使命は研究・教育であり、一般企業とは異なる価値観や意思決定過程により運営されているという側面もあります。そこで、今回は中途採用で入職された大学職員の皆さんにお集まりいただき、転職した理由や入職後に感じた戸惑い、大学で働く魅力など、幅広い話題について議論を交わしていただきたく思います。今回はお名前とお顔を出さない覆面座談会という形にさせていただきますので、率直なご意見をいただければと思います。まずは、皆さんが大学に転職した理由について伺いたく思います。
A氏 私は大学時代に教員免許を取得するなど、もともと教育業界に関心がありました。卒業後は民間企業に就職して18年間勤務しましたが、地方支店での昇進が頭打ちになり、東京への転勤を意識し始めた頃から転職を考えるようになりました。先輩が先に大学職員に転職していたことも、転職先として選択肢に入れた理由です。
B氏 私は総合電機メーカーで5年半、営業職を担当していました。両親が教師をしている家庭で育ったことから教師を目指そうと考えた時期もあったのですが、人に何かを教えるにはまず社会に出ておくべきだと考えて、民間企業に就職する道を選びました。しかし、家族が急病にかかり、当たり前の日常が当たり前ではないことに気付かされました。その時、本当に自分がやりたいことと改めて向き合い、両親が長年従事した教育に対する思いや意志を継ぎたいと考えて教育業界への転職を決意しました。高校までで培った集団意識や基礎学力、知識を社会で働く能力へと昇華させる場所が大学だと考えており、社会を構成する一員となる準備期間にいる大学生は、多くの期待や不安を抱えています。民間企業で働いた経験が一番発揮でき、身近な存在として学生に寄り添いながらサポートできる大学、そして教壇に立たなくても、多角的に教育に携わることができる大学職員は、私にとってとても魅力的でした。
1-2グローバルでアカデミックな
環境を求めて
C氏 私は外資系航空会社で仕事をしていました。地元の支店に就職し、予約管理、収入管理などを担当していました。約20年勤務していたのですが、年々、経費削減、人員削減が続き、地方支店は特に厳しい状況にありました。そのような状況の中、発生したのが新型コロナウイルス感染症です。運航再開のめどが立たず、大都市圏への異動の話となりましたので、転職を決意しました。前職では常に国際的な環境の中で業務を行っていたため、今後もグローバルな環境で働きたいと考えていました。学生時代の先輩が大学職員に転職していたこともきっかけになりました。大学は多様な国籍や背景を持つ教職員・学生が集まる場であり、その環境に魅力を感じて転職を決めました。
D氏 私は外資系企業出身です。新規開拓業務などを担当していたのですが、そこでさまざまなスキルを鍛えられました。大学業界に転職したきっかけは、人を育てる仕事に興味があったからです。大学は研究に携わるアカデミックな組織である一方、国や社会に対して多くの人材を育て、送り出す組織でもあります。最高学府で人を育てることに貢献したい、と思ったのです。

1-3スローで複雑な意思決定プロセス
感じた違和感
音 私自身、大学院を出てから、一度、民間の研究機関で仕事をしたことがあるのですが、やはり民間の企業組織と大学では仕事に対する考え方も仕事の進め方も大きく異なります。そのため、中には入職後に大きなギャップを感じる人も少なくないかと思います。そのあたりについて、皆さんの感想を率直に教えていただけますでしょうか。
B氏 私は、職員に経営的な視点に立った意思決定権や裁量権を発揮する場面が少ないことが課題だと感じました。学内の多くの組織で教員組織が上位にあるため、何をするにしてもお伺いを立てて、決めてもらわないと進められない仕組みになっています。教員に最終意思決定が委ねられることで、積み上げてきた自身の業務の結果やそれに伴う影響に対する責任感が薄まっていると感じています。また、ボトムアップとトップダウンのバランスが取れていないことが多く、結果的にスピーディーな意思決定を阻害しているように感じました。さらに、意思決定に至るプロセスも見えづらく、当初は業務を進めるに当たって誰にアプローチすればいいのかも分かりませんでした。前職で営業を担当していた時は、受注拡大や新規開拓のために自分でストーリーを立て、プランを用意し、社内外のキーマンや意思決定者を巻き込みながら業務を進めていくやり方が染み付いていました。しかし、それを大学で実践しようとすると、与えられている裁量が限られていて、うまく機能しない場面が多々ありました。前職では自身が業務の中心にいる、という感覚が強くありましたが、転職後にその感覚は薄れてしまいました。「線」で仕事をしたいのに、「点」でしか仕事ができなくなってしまう状況に、もどかしさを感じていました。
C氏 前職は、トップダウンでスピード感を持って業務を進める組織体制でした。それに対して大学では、会議を重ねながら慎重に意思決定が行われるため、業務が進むまでに時間がかかる点に、これまでとの大きな違いを感じました。会議の流れや意思決定のプロセスには独自のルールや文化があり、日々その仕組みを学びながら業務に取り組んでいます。また、私は入職後に短期間で部署を転々としたのですが、部署が変わると転職したくらい仕事の内容が変わることに驚きました。職員の多さにも驚かされました。先ほど申し上げた通り、前職では人員削減が進み、年々さまざまな業務を掛け持ちしていましたが、大学では業務が分担されているため、負担が軽減され助かっています。また、それぞれの専門性を生かした対応ができる他、困ったときに相談できる相手がいる安心感や、業務改善に向けた意見交換もしやすいといったメリットも感じています。
1-4出る杭となるべきか
郷に入っては郷に従うべきか
A氏 20年前に入職して驚いたのは、あまりにも緩やかに業務を進めていることでした。おそらく中途採用の方の多くは、「自分が仕事に関わるからには何かしらパフォーマンスを発揮しなければならない」「給与の対価分はしっかり働かないといけない」という意識を強く持って仕事をしてきたと思います。その意識の強さが、民間企業の経験を持つ中途採用の職員と、卒業してすぐに大学職員になった職員とでは大きく異なると感じました。また、入職当時、各部署の説明があった際に「大学は4年間の繰り返しです」と説明した職員がいました。そのような考え方で、定年まで安泰だと思っていることにも驚きました。また、女性管理職が一人もいなかったことにも違和感がありました。入職して間もない頃、褒め言葉のつもりだったのでしょうが、「女性でこんなに働く人を初めて見た」と言われたことがあります。こうしたギャップを埋めるために私に何かできることはないかと常々、考えています。
D氏 私は入職した時に管理職から「出る杭になって変革してほしい」と言われました。その一方で先輩方からは「郷に入れば郷に従えだ」とも言われていました。その中でどうバランスを取りながら仕事をするべきか悩みましたね。入職してからギャップを感じたことは、大学が想像以上に縦割り文化が強い組織だということです。部署間で交流が少なく各々独立した会社のようで、異動すると全く違う立場で仕事をしている。果たしてそれが組織のために最適なのだろうかと思いました。

2-1伝統と文化を持つ私立大学に
新たな風を吹き込む
音 スピード感のなさや組織の縦割りの強さは、民間企業での経験があるからこそ見えてくる課題かと思います。その視点を大学の変革にぜひ生かしていただきたく思います。一方で、大学、特に私立大学には設立の経緯や歴史に裏付けられた伝統や文化があります。それには良い側面もありますが、こだわり過ぎると改革の足かせになりかねません。皆さんは大学の伝統や文化に対してどのようにお考えでしょうか。
A氏 私は「卒業生であるか否か」が大学職員の大きな要素の一つになっているように感じます。卒業生は建学の精神や伝統を理解している前提で見られますが、卒業生ではない中途採用の私は、所属部署によってはアウェーであることを意識させられることがありました。
D氏 本学では、中途採用に力を入れた時期があり、その時期に採用した職員のほとんどが他大学出身者でした。当時の経営陣が、いろいろな血を入れたいという意図で、あえてそういう形を取ったのです。そのため、職場で出身大学を意識することはありませんでした。卒業生とやりとりをする際、「君は何年卒?」と聞かれることもあり、他大学出身者として少し困ることはありましたが、普段の業務では出身大学の影響は皆無に近いと言えます。
B氏 私も同じく、卒業生ではありませんが、あまり気になりません。確かに派閥のようなものを感じる時はありますが、私自身がそうしたことに無関心なだけかもしれません。
C氏 私が勤務するのは地域に根差した地方大学ということもあり、伝統や文化を色濃く感じます。新卒で入職してからずっと勤務している卒業生の職員が多く、地場産業を経営されている卒業生と交流する機会も多数あります。そうしたつながりが強みになっている一方で、大学職員自身が外の風に触れていない、新しい風を吹き込みづらい、と感じることがあります。

2-2ライバルでありながらヨコのつながりも 知的好奇心を刺激する大学という職場
音 大学の独特な組織風土に戸惑いを感じる一方で、民間企業にいたからこその視点で課題を見いだして改善に導いたり、他の人にはないスキルを生かしたりすることもできるかと思います。また、民間企業にはない、大学が持つ魅力を感じたこともあるのではないでしょうか。そういう経験がありましたら教えてください。
D氏 外資系企業にいた頃は競合他社との競争が激しく、敵対した状態になることも珍しくありませんでした。しかし、大学は互いに良好な関係を築いており、交流も盛んで、業界を共に盛り上げて、より良くしていこうという意識が感じられます。職員も他大学の同様の部署と交流があり、常に情報交換をしています。それは大学のとても良いところだと思います。また、学生が成長していく姿を見ることができたり、いろいろな先生方から最新の研究についてお話を聞いて知的好奇心を刺激されたり、他の業界では味わえない魅力が大学にはあります。
2-3業務に、組織に
前職での経験をどう生かすか
B氏 大学を取り巻く環境が厳しくなっているからこそ、外の世界を知る中途採用の職員が力を発揮できるのではないかと思います。しかし、先ほどお話に出たように大学は縦割りの強い組織で、中途採用の職員が何か課題を見つけて改善したとしても、その人が異動すると元に戻ってしまうということも少なくありません。横断的に改善内容を波及させて組織全体を良い方向に変えていきたいのですが、本学の場合はまだそれが難しい状況にあると感じています。縦割構造にはメリットもありますが、他の部署への関心が薄れたり、排他的になったりするなどのセクショナリズムが働きやすいというデメリットもあります。それが、業務の属人化や慣習化を生み、業務の合理化や平準化、組織横断的な思考を阻害してしまいがちです。それを防ぐためにももっと裁量を与えてほしいですし、もっと大きな絵を描いて大学の方向性を話し合うような場を作ってほしいですね。
C氏 私は前職で年齢や職業を問わず、さまざまなお客さまと接してきました。大学でも学生や教員だけでなく、保護者などさまざまな立場の方に対応する必要がありますが、相手の立場に応じた柔軟な対応力やコミュニケーション力が生かされていると感じています。
A氏 前職では担当している業界の情報誌の企画・編集をしていたのですが、大学ではキャリアセンターで学生向けに就職支援の情報誌を作成したり、入試広報に携わったりする中で、前職でのスキルが生かせたと感じています。また、キャリアセンターでは学生からエントリーシートや面接について相談されることが多かったのですが、内容を企業目線で確認したり、採用面接の経験も生かして面接のアドバイスをしたりなど、民間企業に長くいた経験を生かせたのは良かったですね。また、現在は人事を担当していますが、今後は特に専門知識の必要な部門において、中途採用に力を入れていこうと考えています。民間企業で求められる柔軟な発想や中長期的な視点を身に付けた人材を採用し、全体の意識を向上させていきたいと考えています。

2-4職員に欠かせない、
学びと交流の機会
音 大学は非常に多様性が求められる組織です。その点では、中途採用の職員の存在は、大学に対してさらなる多様性を与えるものだと思います。中途採用の方々が、民間企業と大学との間にある壁を乗り越えてもっと活躍できるようにするために、これまで取り組まれてきたこと、あるいは大学に望むことがあればお話しください。
D氏 今後、大学が時代を切り拓いていけるかどうかは職員組織の「人」次第だと感じています。そのためには、やはり教育や研修を通してもっと広い視野と柔軟な思考を身に付けなければなりません。大学では年配になればなるほど、視野が狭く、考え方も凝り固まっているように感じます。そこにテコ入れするには、やる気のある職員や仕事をした職員が報われる給与報酬体系や組織制度が必要です。やってもやらなくても同じでは、どんどん楽な方にシフトしてしまいますから。また、裁判官は民間企業などで研修を行う派遣型研修が実施されていますが、大学でも新卒の職員に民間企業を経験してもらい、広い視野と柔軟な思考を学んでもらうといいかもしれません。
A氏 中途採用の職員が即戦力のつもりで入職しても、業界が違うと分からないことが多過ぎて、自分のスキルがどう生かせるのか見当も付かないことがあります。そうした事態を解消するために、「この人はこういうスキルを持っています」と人事側が責任を持って各部局に説明して理解してもらう仕組みを作ることが重要だと思います。そうすることで、現場が人材を持て余す期間を短縮できるのではないでしょうか。また、新卒採用の職員は同期との結束が強いのですが、中途採用の場合はそうした人間関係を得にくくコミュニケーションが取りづらい面があります。それに対して、「経験者採用者交流会」のようなヨコのつながりを作り、気軽に悩みを相談し合えるような場を設けられればと思っています。
C氏 学内の研修会や教職員合同行事などに、積極的に参加するよう心掛けています。そうした場で得られる情報や、他部署の方とのヨコのつながりが、後に仕事を進める上で大きな助けになると感じているからです。本学では、新卒・中途関係なく新規入職した教職員が一緒に受ける研修や、先輩職員との研修などが行われており、とてもいい機会だと思う一方、そこでの議論や提言がその場限りで終わっているようにも感じています。
B氏 私は、即戦力の定義が曖昧であることが問題だと考えています。「今の仕組みにマッチする即戦力が欲しい」のか、「今の仕組みを変革して組織を良い方向に変えていく即戦力が欲しい」のか、採用時点で明確に示す必要があると思います。入職後は中途採用者を集めたプログラムを実施し、前職の業態や業務内容を参照しながら大学経営や業務について議論し、共に「こうあるべき」というビジョンを共有する仕組みを作ることが有効だと感じます。また、中途採用者が配属された部署内には何かしらのプラス要素が働くと思いますが、そのプラス要素が組織全体には波及せず、縦割構造の中に埋もれてしまうケースが多いと思います。それを防ぐには中途採用の職員同士がしっかり”横串”を通して部署間をつなげられるような仕組みができていかないとダメだと思います。ただし、中途採用者のノウハウや見識が大学組織にとって100%プラスに働くわけではないため、新卒者と中途採用者が協働して方向性を議論し、自分たちの業務を自分たちで創っていく、そんな組織横断型の業務検討プロジェクトチームを設置するなど、組織全体としての体制を作ることも必要だと思います。業務改善のための研修も行われていますが、せっかく時間を割いて議論して、提言まで持っていくのに、Cさんがおっしゃったように、その場限りの話で終わってしまうことが多いです。「研修を研修で終わらせない」という意識を強く持つことも大事なのではないでしょうか。
3-1大学存続の鍵となる職員として

音 最後に、大学における中途採用職員の将来にどのような展望を描いているか、あるいは他にご意見があればお聞かせください。
A氏 人事側としては、大学に新たな風を吹き込んでくれる、大学で働くことの意義を高く持つ方をしっかり選考していきたいと思います。また、人材を募集する際にも綺麗事を言うのではなく、教育・研究・社会貢献が学校教育法で定められた大学の使命であり、それらにしっかり取り組まなければ永続的に発展できないことも伝え、その上で応募してくれる人を採用したいと考えています。そうして採用した人たちが生き生きと働ける環境を作ることが私たちの急務ではないでしょうか。
C氏 地方の私立大学は存続が大変厳しい状況にあります。本学がある地域では、私立大学のほとんどが定員割れになっています。そのような中、学生へのサービスの質を高めることが大学の魅力につながり、結果的に入学希望者の増加にもつながると考えています。しかし、おろそかな対応をしてしまう場面も見受けられ、残念に思うこともあります。学生に親身になって対応していれば、それは保護者にも伝わりますし、その周囲にも伝わっていきます。ですから、大学で働く一人一人が「日々の仕事の積み重ねが、学生獲得や大学の評価につながる」という意識を持つことが重要だと感じます。

3-2大学職員としての矜持(きょうじ)を持つ
D氏 ネットやSNSでは、中途採用された大学職員が「大学はラクで待遇がいい究極のホワイト業界だからどんどん転身すべき」とうたい、大学職員中途採用試験対策セミナーのようなものを開講しているのが散見されます。大学を取り巻く環境は少子化が進行しており、甘い言葉で転職を勧めたり、希望したりする人がいるのは残念でなりません。やはり、大学を改善する即戦力として期待されており、将来の社会を担う人材を育てるという気持ちや気概を持って教育業界を志してほしいと思います。
B氏 われわれは”事務”職員ではありますが、大学教育を担うスタッフの一人なのだということを念頭に全ての業務に当たるべきだと考えています。そうでないと、Dさんが指摘されたような面から転職する人が出てきますし、そうした姿勢がサービスや業務の質の低下にもつながるのだと思います。職員一人一人が、大学職員として働くことに対する自負や誇りをしっかりと持つべきであり、それを研修でしっかり植え付けることが、新卒・中途採用にかかわらず重要になると思います。
音 皆さんのお話を聞いて、大学ではやはり「人」が財産であること。それを生かす仕組みが大切であることがよく分かりました。本日はありがとうございました。