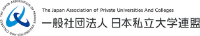MEMBER
植田 光雄
関西大学学長室次長・
大阪・関西万博推進プロジェクト事務局

栗本 聡
大阪大学共創機構機構長補佐
(兼)大阪大学2025年日本国際博覧会推進室長

長谷川 哲
立命館大学総務部担当次長(OIC地域連携担当)、
立命館万博連携推進本部事務局

木嶋 淳
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
広報・コミュニケーション局地域・観光部長
(2025年1月取材時/2025年3月より、広報・コミュニケーション局担当部長)

司会音 好宏
上智大学文学部教授、広報・情報委員会大学時報分科会分科会長

1-1参加型万博だからこそ
大学にできること
音 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)がまもなく開催されます。「TEAM EXPO 2025」プログラムという、個人や大学が万博の主人公となって参加できる取り組みが用意されているなど、参加型の万博となっていることもあり、特に関西の大学はさまざまな形で万博に関わっていると聞いています。そこで今回は、万博開催に向けた各大学の取り組みについてお話を伺い、意見を交わすことで、大学にとって万博をより意義深いものにしていきたいと思います。最初に大阪・関西万博に参画することになった経緯についてお聞かせください。
植田 関西大学は大阪で生まれ、大阪とともに成長してきた大学です。それだけに大阪から世界に発信する万博という大きなイベントに関われることは滅多にない大きなチャンスだと考えています。本学は、創立130周年を迎えた2016年に、「Kandai Vision 150」という将来ビジョンを制定しました。その中には「未来を問い、そして挑戦する。」というメッセージが込められています。今回の大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」は、それとも合致するものだと考えています。そのため、当初から大学として万博に積極的に関わっていきたいという強い思いを持っていました。そこで、理事長と学長の下に「2025大阪・関西万博に向けた協力・推進プロジェクトチーム」を設置して準備を進めてきました。特に理事長の万博に対する思いは強く、昨年の入学式の祝辞では、1970年の万博で世界の人々と触れ合ったことで視野が大きく広がったという自身のエピソードが披露され、そうした熱い思いが多くの学生にも伝わりました。
1-2教育を目的とする万博の地元開催
参加しない理由はない
長谷川 大阪・関西万博が開催される2025年は、立命館学園創立125周年を迎える年であり、大阪いばらきキャンパスを開設してちょうど10年となる年でもあります。それに合わせて催されるさまざまな記念行事を万博と連動させることでさらに盛り上げたいということが、本学園が万博に参画する理由の一つです。また、本学園は、2030年までの10年間の中期計画として「学園ビジョンR2030」を2020年に策定しました。その中間地点の2025年に万博に参画することで、次の5年間の飛躍につなげたいという考えもありました。 そもそも国際博覧会条約の第一条に、博覧会とは「公衆の教育を主たる目的とする催し」だと定義されています。それを踏まえると、関西にキャンパスを構える教育機関が大阪で開催される万博に関わらないという選択肢はあり得ません。万博には多くの企業が協賛されていますが、教育機関はあまり多くない印象です。国内では万博開催に消極的な意見もありますが、ある意味それは大人の事情であって、子どもたちや若者にとってはこんな貴重な機会はありません。せっかく在学中に万博が開催されるのであれば、生徒や学生が何らかの形で参画する機会を作ってあげたいという思いも、協賛を決めた背景にありました。

1-3若者の道しるべとなる
イベントを目指す
栗本 大阪大学は、大阪・関西万博誘致が決まった翌年の2019年に「大阪大学2025年日本国際博覧会推進委員会」を立ち上げました。委員会は「いのち部会」「先端技術体験部会」「学生部会」「国際部会」という4つの部会で活動を推進しており、その事務局として2025年日本国際博覧会推進室が設置され、私は現在、室長を務めています。推進室では、自治体や企業など学内外のさまざまな組織と交流し、万博に向けた機運醸成に取り組んでいます。また、「Contribution to All Lives beyond 2025」というビジョンを掲げ、大阪・関西万博の開催に貢献する活動を続けています。
音 日本国際博覧会協会で地域・観光部長を務めておられる木嶋さんには、事務局としてどのような考えの下に大学との連携を進めてきたのか、お聞かせいただきたいと思います。
木嶋 私が所属する公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、2019年1月、国・地方自治体・経済界の協力の下に設立されました。私は2024年から地域・観光部の部長を務め、日本各地の魅力を伝える活動に従事しています。一般的に、万博というと大まかなイメージはあるけれど、具体的にどんなものかは分からないという人も少なくありません。そのため、事務局ではまず「万博とは何か」ということを伝えるために広報活動を行ってきました。大学との取り組みとしては、事務局スタッフによる講義の実施のほか、大学生協と連携してポスターを掲出させていただくなどの活動を続けてきました。万博は最先端の技術や文化に触れられるだけでなく、世界中の人々と国際交流ができる場です。大学生を中心とした若い方々にとっては、将来、自分が進みたい道を考える上での道しるべの機会となるはずです。学生の皆さんにはぜひ、会場に足を運んで万博を経験してほしいと思っています。
2-1期待を超えた学生たちの熱意
音 木嶋さんから大学での講義実施についてお話がありましたが、関東の大学でも少しずつ、サークル活動や先ほどの講義のような形で、万博開催に向けて活発化していると聞いています。 さて、各大学がそれぞれのビジョンや理念の下に準備を進めてこられたことが分かりました。続いて、これまで具体的にどのような取り組みをされてきたのか伺いたいと思います。
植田 本学は「大阪ヘルスケアパビリオン」で実施される中小企業・スタートアップの支援事業企画「リボーンチャレンジ」に出展します。中小企業・スタートアップの優れた技術力や魅力、象徴的な成果を発信するもので、26週にわたり出展がありますが、本学は教育機関として唯一選定されました。このように、学際的な研究や社会連携活動を通して存在感をアピールできるという意義もありますが、未来を担う学生の教育に資するという点でも大きな意義を持っていると考えています。本学では、学生の教育にSDGsや万博を積極的に織り交ぜており、独自にSDGsや万博に関連する講義を設置するなどの取り組みを行ってきました。 2023年には大学公認の学生コミュニティ「関大万博部」が立ち上がるなど、学生が中心となって万博に主体的に関わる動きも出てきました。発足当初の部員数は30名程度でしたが、現在では140名近くが参加して精力的に活動しています。関大万博部には関西圏以外の地域から進学してきた学生も多く参加しているのですが、本学を選んだ理由を聞いてみると「関大が万博に積極的だから」と答えた学生がいたことに驚きました。地域によって万博に対する温度差があるといわれることもありますが、そういうことを気にせずに自分が興味のあることや、やりたいことをしっかり考えて行動できる学生がいることに心強さを感じました。 昨年4月、日本国際博覧会協会の協力の下、学内で公式ボランティア募集の説明会を開催したところ、700名以上の応募があり、学生の万博に対する思いの強さを改めて実感しました。また、本学は「TEAM EXPO 2025」の共創パートナーとなっており、学生たちを中心に多数の「共創チャレンジ」を行っています。現在は、万博会場の「TEAM EXPOパビリオン」をはじめ、さまざまな催事エリア等でその成果をできるだけ多く展示・発表できるように、支援に力を入れているところです。


2-2大学の全キャンパス・
全学部の学生が参画
学園内の活動は全国規模に
長谷川 本学は2022年に大阪・関西万博への協賛を決定しました。それを機に万博に関わりたい学生を募集したのですが、当時はまださほど機運が高まっておらず、20名程度だろうと予想していました。しかし、驚いたことに約100名の応募があったのです。何人かに応募の理由を聞いてみると、具体的なイメージはないが「何となく面白そう」というシンプルな動機が多く、若いエネルギーを発散する場を求めているのだと感じました。大阪だけでなく滋賀や京都のキャンパスの全ての学部から応募があり、万博への関心の高さがうかがえました。 2023年4月には、それらの学生たちで万博学生委員会を設立し「おおきに」という名称で活動がスタートしました。「おおきに」のメンバーは、今では250名近くに増加しており、開幕が近づくにつれ関心の高まりを実感しています。「おおきに」では、環境問題や多様性・異文化理解、ジェンダー、日本文化など、さまざまなテーマを自ら設定し、班ごとに活動しています。本学が協賛しているのは、ジャズピアニストでありながら数学研究者で、「STEAM教育」にも力を入れている中島さち子さんがプロデュースするテーマ事業「いのちの遊び場 クラゲ館」ですが、そこにはワークショップスペースも用意され、参加者の創造性によって成長するパビリオンというのがコンセプトの一つになっています。「おおきに」各班によるワークショップも多数出展予定ですが、現在は、北海道にある附属校(立命館慶祥中学高等学校)から九州の立命館アジア太平洋大学まで全ての学校・大学において、ワークショップや学生活動の発表の場としてクラゲ館や万博への期待が高まっており、学園内の活動はほぼ全国的に展開されつつあります。 その他には、2024年9月に開催された大屋根リング記念式典で、本学の書道部の学生2名が書道パフォーマンスを行い、2メートル四方の大きな和紙に「いのち輝く輪をつなごう!」という力強い文字を揮毫(きごう)しました。この作品は、会期中会場内で展示される予定と伺っています。


2-3大阪大学の4つの取り組み
学生の参画・経験・成長を重視
栗本 本学は大きく分けて4つの取り組みを行っています。1つ目は、未来社会に向けた研究の発信です。日本国際博覧会協会や自治体、企業と連携し、コンソーシアムやスタートアップの形で研究成果の発信に取り組んでいます。2つ目は、「いのち」に向き合う教育・研究の推進です。本学は当初から、「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマに基づいて、「いのち」をテーマにした「ソフトレガシー」を残していきたいと考えてきました。そこで、本学を事務局として、関西経済3団体と一緒に「いのち会議」という事業を立ち上げました。未来社会に向けて全てのいのちが輝くにはどのようなアクションを起こさなければならないのかということを、さまざまな方々と議論し、万博会期中にその成果を「いのち宣言」として発信する予定です。3つ目は、海外との連携です。万博で多くの人が来日するこの機会に、海外大学とのネットワークを強化し、共創活動を推進していきたいと考えています。4つ目が、次代を担う若者や学生の参画です。学生たちに万博を通していろいろな経験をしてもらうことで成長につなげてほしいと考えています。そのため、推進委員会の学生部会や、万博に関わる活動に取り組む学生団体の支援にも力を入れています。ユニークなのが、「a-tune」という学生団体の活動です。「音楽を通じて言葉の壁や、国内外で問題になっている社会の分断を超える」というコンセプトの下、コロナ禍の間に立ち上げられ、オンラインで海外の学生と合奏するなどの活動を行ってきました。推進室でも活動を支援してきましたが、近年、多くの人に知られるようになり、万博の催事会場で世界をつないだ演奏会を開催できることになりました。
音 今、社会に貢献したいという気持ちを持った学生が多いことは実感していましたが、万博という場ができたことで、学生たちがその思いを発露できているように感じました。一方で、万博協会事務局としては、大学や学生に対してどのような期待を寄せているのでしょうか。
木嶋 お集まりいただいている3大学には、さまざまな連携を作り出すために用意した「TEAM EXPO 2025」プログラムに積極的に参加していただいており、感謝しています。日本は少子高齢化をはじめとしたさまざまな課題を抱えています。また、世界に目を転じると紛争が絶えないなど、分断の時代にあるとも言えます。そんな現代において、万博を通して社会貢献をしたいと考える学生が多くいることをとても心強く感じます。これからの新たな時代を若い皆さまにつくっていただくべく、万博で得た経験を生かして、今後どのような社会貢献ができるかを考えるきっかけにしてほしいと思います。
2-470年万博からの大きな変化
大学に求められるさまざまな連携と
イノベーション創出
音 私も2021年に東京オリンピックが開催された時、学生がボランティアに参加して成長する姿を目にしました。お話を聞いていると、万博に関するさまざまな活動を通して、開催を前にすでに学生たちに良い変化が表れているように思います。大学として万博に参画することで、ほかにどのような成果を期待しているかをお聞かせください。
植田 本学はこれまでに30以上の「TEAM EXPO 2025」プログラム共創チャレンジを登録しています。大学の中ではかなり多い方ではないでしょうか。その背景には、2021年に導入したSDGsパートナー制度の存在があります。学生たちが自治体や企業など実社会とつながってSDGsの達成に向けた取り組みを行うというもので、今では70以上の団体・組織に参画いただいています。その取り組みの一部は、今回の共創チャレンジにもつながっています。前回の大阪万博が開催された1970年当時は、まだ大学と企業が連携することが半ばタブー視されていたような時代でした。しかし、現代は社会連携、地域連携、産官学連携が当たり前の時代ですし、むしろそれにより生み出されるイノベーションが重要視されています。万博をきっかけにそうした共創がより活性化することを期待しています。
長谷川 「いのちの遊び場 クラゲ館」は、参加者と一緒に作り上げていくオープンなスタイルのパビリオンで、外国人も障害がある人も、大人も子どもも、多様な人が関わることを理想としています。月1回、協賛企業が集まる会議が、東京か大阪で行われてきましたが、大阪で開催する場合は本学の大阪いばらきキャンパスを使っていただいています。毎回、本学を含む協賛者(2025年1月現在21社)から70〜80名が集まって意見を交わすのですが、そこに本学の学生も参加させていただいています。会議では企業の機密事項の話題が出ることもあるため、学生には秘密保持誓約書を書いてもらうのですが、中島プロデューサーからはそういう手続きを踏んででも学生の声を聞きたいという要望をいただいています。当初学生の参加は少なめでしたが、回を重ねるごとに増え、積極的に発言する学生も見られるようになりました。学生にも企業の方々と関わりたいという思いがあるのだと思います。学生時代に社会と関わり、成長していく姿を見ていると、大学職員としてうれしくなります。 また万博と関わる中で、学生たちに、授業やゼミ、学部、学年、キャンパス、さらには大学の枠をも超えた新たなコミュニティが自然発生的に生まれてきたことも印象的でした。その中でリーダーやサブリーダーが現れて、組織として成立している。このような現象が起きるのは、やはり万博があってこそだと思います。
2-5万博ならではのチャンスを生かす
キャンパス外での学びは宝
栗本 共同研究という形の産学連携とは異なり、万博では企画を進めるに当たって企業がいかに学生の視点を取り入れていくかが重要になります。企業の方と話していても、学生に大きな期待を寄せていることが伝わってきます。一方、学生もアルバイトや就職活動などで企業と関わるのとは違った形で関係を築けることが、大きな刺激になっているようです。こういう形の企業と学生とのつながりが、万博が終わった後も続いていってほしいと思います。 また、先ほどお話しした「a-tune」はイベントを開催する資金を調達するために独自にクラウドファンディングを行ったり、企業から寄付を募ったりする中で、顕著な成長を見せてくれました。そうした姿が周りにも伝わり、ほかにも万博に向けて何かやりたいという機運が高まって、独自に「TEAM EXPO 2025」に応募する団体も出てきました。そうした学生たちの熱に応えるべく、大学として「TEAM EXPO 2025」のパビリオンの一部を借りて、学生が未来について考える「阪大万博DAY」を実施することを決定しました。学生と話していてよく聞こえてくるのは、「万博がなければ、他大学の学生団体や企業の人たちとこれほど交流できる機会は、絶対になかった」ということです。準備などで苦労することもあると思いますが、学生たちにはこの機会を存分に楽しんで、一生の宝になるような思い出を作ってほしいと思います。 さらに、万博は学生だけでなく教員にもプラスの影響を与えていると思います。大学としても、教員に対して万博でこのような研究成果の発信の機会があるといった情報は伝えてきましたが、万博を研究に生かしたいという潜在的なニーズはまだまだあるのではないかと思っています。
音 大学は多様な意見を持つ人々が共存している場であり、万博開催に関しても、ポジティブな意見、ネガティブな意見の両方が発信される場でもあります。そうした点も含めて、大学に対する関わり方が、ほかの組織と異なると感じる点があれば教えてください。
木嶋 地域・観光部では、大学のほかに地方自治体や観光協会などの団体ともやり取りをしています。万博で日本各地の観光資源をアピールしてもらい、旅行への興味を持ってもらうことで、万博をきっかけに地方、そして日本全体を活性化させることが狙いです。大学の目的は研究成果のアピールや学生の教育、地方自治体・観光団体の目的は観光客の誘致と、異なりはしますが、さまざまな交流を通じて社会を活性化させるという最終的なゴールは同じだと思います。それを信じて、参画していただいている各団体の期待に沿えるようなイベントにしていきたいと考えています。
3-1万博をきっかけに、
その先を見据えた取り組みを

音 いよいよ4月から大阪・関西万博が開催されますが、それに向けての抱負がありましたらお聞かせください。
植田 本学は、先ほどお話しした大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンチャレンジに、大学では唯一の実施主体として出展しています。そこでは、共同研究を通してこれから社会にイノベーションを起こしていくであろう大阪の中小企業やスタートアップ、大学発ベンチャーなどと連携し、さまざまなシーズを世界の人たちに向けて発信していきます。本学の研究力についてしっかり伝えることで、万博を意義あるものにしたいと考えています。また、学生には万博に主体的に関わることで、大きく視野を広げてもらいたいと思います。万博会場で自分たちの活動成果を世界に発信できるということも、学生たちのモチベーションの一つになっていると思います。しかし、発表がゴールではなく一つの通過点として、大阪・関西万博で得られた経験やつながりを生かし、さらにその先につなげていってほしいですし、万博がそういう機会になることを期待しています。
長谷川 生徒や学生たちには、「万博って何だか面白そう」という軽いきっかけで構わないので、まずは万博に関心を持ち、できれば関わってほしいと思います。それはただ見に行くだけでもいいのです。私は小学生の頃、1970年の大阪万博を見学に行きました。その時は親に連れられて行っただけでしたが、それでも万博会場で目にしたものは今でも強く印象に残っており、何らかの形でその後の人生に影響を与えてきたと感じます。当時を経験しているわれわれ世代が、現在、若者を教育する立場になっていますが、おそらく70年万博を経験した誰もが、子どもの成長において万博は有効だという意識を持っているのではないでしょうか。万博会場へ足を運べば珍しい形の建物があり、いろいろな国の人と出会い言葉を聞き、さまざまな文化に触れることでしょう。それらを体験することは、一言では言い表せない大きな意義があり、人間の成長過程で重要となる“発見”や“気付き”を得られるきっかけになる
研究との関わりでは、2023年設立の立命館大学宇宙地球探査研究センターが主となった研究展示のほか、さまざまな研究の発表展示も行う予定です。そうした先端研究分野の展示を通して、若者の夢や企業とのコラボレーションへとつながっていくことも期待しています。

3-2リアルでしか得られない体験価値
栗本 万博開催中のイベントなど、現時点(2025年1月)で決まっていないことが実はたくさんあるのです。例えば、各国のナショナルデーにどんなゲストが来て、どんな催しが行われるかなど、まだ全てが明らかにされているわけではありません。今後、海外から「こういう研究者と交流の場を持ちたい」といった依頼が来る可能性もあり、準備をしておかなければならないと思っています。また、いろいろな組織・団体がSDGsなど8つのテーマについてディスカッションを行う、テーマウィークというイベントが開催されます。それにスピーカーとして教員が呼ばれる可能性もありますし、学生が参加できる可能性もあります。そうした情報収集をしっかりしながら、万博という機会を存分に生かしたいと思います。
音 万博協会事務局としてはどのような万博となることを期待されていますか。
木嶋 将来の日本や世界を築いていく若者にとって、万博が一つの旅のような場になることを期待しています。55年前の大阪万博の時と違い、インターネットにより世界はぐっと身近にはなりました。画面を通して簡単に世界の状況を見ることができるようになりましたが、実際に触れて感じる体験は、インターネットを通じた体験よりもはるかに価値があると思っています。万博は、さまざまな最先端技術、世界各地、日本各地の伝統文化などにじかに触れられる貴重な機会です。ぜひご来場いただき、その魅力を感じ取ってほしいと思います。
音 私も大阪・関西万博の開催を楽しみにしています。皆さんにとって良いイベントになるように願っています。本日はありがとうございました。